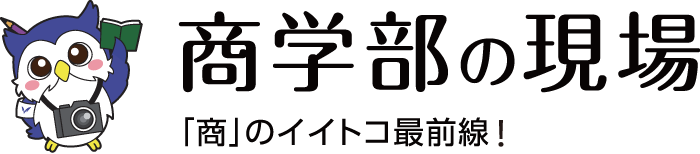2025.03.17
林野庁「令和6年北の国・森林づくり技術交流発表会」で水野勝之ゼミ学生と高校生が共同報告
水野 勝之(担当教員)
2025年2月19日、林野庁「令和6年北の国・森林づくり技術交流発表会」が北海道大学学術交流会館で開催されました。水野勝之ゼミ生三浦佳大さん、横内由希子さん(ともに2年)、杉並学院高等学校本多真理さん(3年生)、帯広農業高等学校久田なつみさん(2年生)が共同報告を行いました。テーマは「大学生、帯広と東京の高校生の柳の有効活用の共同研究-柳を通じてのふれあい木育研究-」でした。林で雑草扱いされている柳の木の有効利用を提案しました。水野ゼミは2年連続奨励賞を受賞していましたので3年連続を目指しましたが、今回は残念な結果になりました。学生や生徒たちも反省すべき点を整理し、また来年度トライする気持ちになっていました。

写真1:発表シーン
この発表の準備では、明治大学商学部兼任講師土居拓務氏、杉並学院高等学校講師月岡忠さん(明治大学大学院商学研究科博士前期課程2年生)も学生たちの発表の練習指導や書類作成を手伝ってくださいました。
学生、参加者のコメント
横内由希子さん(商学部2年生)
私は今回、庭師の方や高校生の皆さんと交流するまでそもそも「柳」がどのような植物で普段どのように利用されているのかも知りませんでした。しかし、柳をもっと有効活用したい!という皆さんの想いと触れ合うことで一緒にこの企画を盛り上げたいと感じました。林業に詳しい方々と共にアイデアを出し、議論できたことは貴重な経験になりました。技術交流会は私たちの発表結果としては悔しいものになりましたが、森林に精通した方々の取り組みやアイデアを学ぶことができ、森林に関連した企画が多岐に渡るうえ、とても重要な話題であることも改めて感じました。
本多真理さん(杉並学院高校3年生)
技術交流会における多くの発表者は、何年にも及ぶ実証実験や、専門的な知見による研究発表が多かったです。私たちの発表はまだまだ改善する部分が多い段階であることを痛感しました。一方で、明治大学生と東京と北海道の高校生による共同研究を通じて、他分野からの視点の重要性にも気がつきました。ここで研究を終わらせるのではなく、継続的に、商学と地域活性化の知識を組み込んだ研究を行なっていきいと考えております。そして、必ず、来年度の技術交流会では審査員に認めていただける様、全力を尽くして発表を行いたいと思います。
月岡忠さん(明治大学大学院商学研究科博士前期課程2年生)
明治大学生に東京と北海道の高校生による広域高大連携事業は、浦幌町でのフィールドワークを元に、その後はオンライン機器を利用した共同作業によって研究発表に至った。このような事例は、今後の大学と地域の高校との連携事業による広域高大連携事業のモデルケースとなることが期待できる。


写真2、3:発表会の看板前にて