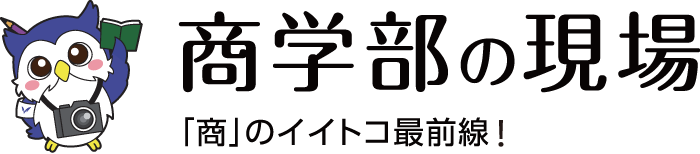2025.01.21
特別テーマ研究科目A/B_社会調査法「千葉県房総半島道の駅バスツアー」成果報告
松尾隆策(担当教員)
明治大学商学部2024年度「特別テーマ研究科目A/B_社会調査法」(担当:松尾隆策) において「道の駅バスツアー」を実施しました。当日の行程プログラムは以下の通りです。
プログラム
【日時】2024年11月23日(土) 9:00〜19:00
【行程】
明治大学和泉キャンパス===道の駅「発酵の里こうざき」==道の駅「水の郷さわら」
9:00発 10:30/11:30 12:00/13:30(昼食)
道の駅「季楽里あさひ」===道の駅「みのりの郷 東金」==明治大学和泉キャンパス
14:30/15:00 16:00/17:00 19:00着
バスツアーには、「特別テーマ研究科目A/B_社会調査法」の履修学生22名のうち12名が参加しました。加えて、以下の明治大学「道の駅」研究所の客員研究員の先生方4名に、外部専門家委員としてご同行いただきました。
・吉兼秀典氏 八千代エンジニヤリング株式会社専務取締役
・大山高志氏 八千代エンジニヤリング株式会社国内事業部専門課長
・山本曉美氏 東京大学政策研究大学院学際情報学府博士後期課程
・森生文乃氏 漫画家
バスツアーで訪れた千葉県内の「道の駅」の名称および所在地は以下のとおりです。
- 「発酵の里こうざき」: 〒289-0224神崎町松崎855
- 「水の郷さわら」道の駅 : 〒287-0003香取市佐原イ3981番地2
同 川の駅 :〒287-0003香取市佐原イ4051番地3
- 「季楽里あさひ」:〒289-2511 千葉県旭市イの5238番地
- 「みのりの郷 東金」所在地:〒283-0005千葉県東金市田間1300-3
各「道の駅」では、地域活性化の取り組みについて、駅内の休憩施設、情報発信施設、地域連携施設(農産物直売所、特産品販売所)などを調査し、そこで働いておられるスタッフの方々にインタビューを行いました。なかでも、「水の郷さわら」と「みのりの郷 東金」では、駅長さんのお話を伺いました。各「道の駅」での調査の概要は以下のようになります。
最初に訪問した道の駅「発酵の里 こうざき」は、"発酵"をテーマとした全国でも非常に珍しい「道の駅」です。特産品販売所「発酵市場」では、地元千葉県神崎町で生産された「神崎納豆」のほか、全国で生産された有名な塩麹、お味噌、日本酒などの発酵食品が店頭に並んでいました。また、販売所に隣接したレストラン「オリゼ」では、麹菌を意味する"オリゼ"の名のとおり、米糀味噌、塩麹など、全て発酵食品を使用したメニューが提供されていました。1つのキーワードをコンセプトとした特徴のある運営は、SNSをはじめ多くのメディアで取り上げられ、消費者に新鮮な印象を与えていることが、地域外からの誘客効果を生んでいると感じました。
次に訪れた「水の郷さわら」では、「川の駅」の2階にある大会議室で、駅長の吉田玄氏から、道の駅・川の駅「水の郷さわら」設立に至った経緯についてお話を伺いました。同駅は、疲弊した佐原地域の古い街並(重要伝統的建造物群保存地区)の活性化を目的として、旧佐原市(現在の香取市)、千葉県、国土交通省が連携して「佐原広域交流拠点PFI事業」として設置されたこと。そして利根川水系の防災の観点から、いわゆるスーパー堤防事業(高規格堤防整備事業、河川防災ステーション整備事業)による「防災」「水辺利用」「文化・交通交流」の拠点として国交省所管の「川の駅」と共に「道の駅」が整備されたことを伺いました。
利根川水系の堤防事業は、江戸時代に徳川家康の命により行われた同地域を流れる「利根川」の治水事業の流れを汲む大規模インフラ政策であり、平時には「水辺交流センター」として観光船の運行、観光ボートやレンタサイクルの貸し出しのほか、物販、喫茶などの収益を生む施設として機能しているそうです。防災拠点としての平時利用についての貴重なお話を伺って「道の駅」の防災機能の重要性を改めて認識しました。
3番目に訪問した「季楽里 あさひ」では、地元の農産物による品揃え豊富な直売所を見学しました。国内トップクラスの生産額を誇る地元産のトマトをはじめ、キュウリ、春菊、パセリなど、バラエティ豊かな新鮮野菜・果物が内外の利用者にとても人気で、海匝(かいそう)漁業組合と連携したハマグリ・赤貝などの貝類、イワシ、しらすなどの新鮮な魚が販売されていました。
4番目に訪問した「みのりの郷東金」では、駅長の内山大史氏にお話を伺いました。東金には、約400年前に徳川家康が東金地域で鷹狩りを行った跡や、船橋市から東金に至る「御成街道」などが、江戸時代の面影を残す観光スポットになっているというお話を伺いました。農産物直売所では、江戸時代から盛んな九十九里浜の気候と風土で育てられた「マキ」が販売されていることが印象的でした。
本バスツアーは、今年度より始まりました「特別テーマ研究科目A/B_社会調査法」(担当:松尾)におけるアクティブラーニングの一環として実施したフィールドワークで、「道の駅」による地域活性化の取り組みを実際に体感するという目的で実施されました。本バスツアーにご同行いただきました外部専門家委員の諸先生も、現地の方々のお話に興味深く耳を傾けておられました。本ツアーの実施により、授業内で実施した千葉県「道の駅」に対する駅長アンケートの調査結果の分析が、より実態に即したものとなり、地元の具体的な活性化の取り組みをより効果的に地域活性化の政策提案につなげられることが期待されます。なお、本活動は「2024年度 明治大学社会連携活動助成金」の支援を受けて実施されました。改めまして、ここに感謝いたします。
写真1 道の駅・川の駅「水の郷さわら」での研究会の様子(左)と水辺交流センターでの集合写真(右:中央が吉田駅長)
写真2 道の駅「季楽里 あさひ」での様子
写真3 道の駅「みのりの郷 東金」での内山駅長による説明会の様子