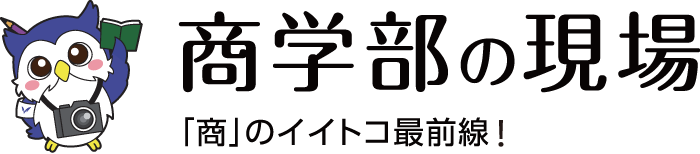2025.03.10
学園祭報告書
森永由紀ゼミナール 2・3・4年
テーマ: 環境問題をはじめとする社会の出来事に当事者意識をもつこと
日 時: 2024年11月1日(明大祭初日)
場 所: 和泉キャンパス ラーニングスクエア LS401教室
**************
展示内容
1.「日本の原発のこれまでとこれから」(3年生担当)
2024年6月に実施した福島合宿を通じて学んだ福島第一原子力発電所事故について展示を行いました。時系列に沿った年表を用いて、3.11の原発事故に関する過去・現在・未来の影響を解説しました。
2.「杉並区にこんな公営住宅があったら」「若者はどうして選挙に行かないのか」(2年生担当)
社会問題への当事者意識を育むため、10年後にどのような町に暮らしたいかについてのアイデアを出し合い、ポスター形式で展示しました。
3. 「つかめる水」と「環境かるた」(4年生担当)
来場者が遊びながら学べる体験型コーナーを2つ設置しました。
****************
展示の詳細
1.福島関連展示

写真1 福島事故関連の年表
・東日本大震災は、地震・津波・原発事故が重なった戦後最悪の自然災害でした。本展示では、3.11原発事故に関する年表を「事故前」と「事故後」に分けて作成し、以下のような内容を解説しました。
・日本の原発の歴史: 日本に原発が導入され、2006年までに54基の原発が建設された。
・事故のリスク: 2011年の事故以前から、地震・津波が原発事故を引き起こす可能性が地球科学の専門家らより指摘されていた。
2001年)津波地震の研究者らが869年の貞観地震(M8.3〜8.6)が東北地方沿岸で大津波を引き起こしたことを示す研究を発表。
2008年)東京電力の社内試算で、福島第一原発に最大15.7mの津波が来る可能性が指摘。(3.11に、実際には15.5mの津波が観測された)
2010年) 政府の地震調査委員会が「貞観地震のような巨大地震が福島沖でも発生する可能性がある」と発表。
・避難の影響: 3.11後の原発事故により最大16万人が避難。被ばくによる直接的な死者は公式に報告されていないが、避難や生活環境の悪化による死亡者数は福島 県 の報告で2021年時点で約2,332人。
・原発労働者の実態: 原発労働者は平常運転時でも日常的に被ばくしている。事故後は毎日4,000人以上が廃炉作業に従事している。
・再稼働の現状: 原発事故後、川内原発を皮切りに再稼働が始まっているが、避難計画の不備が懸念されている。2024年11月現在の稼働数は13基。
・福島の廃炉問題: 廃炉費用は莫大であり、今後40年間にわたり電気料金に転嫁される。 廃炉は30年で完了する予定とされるが、必ずしも順調には進んでいない。
・新規原発建設の資金調達: ABS(電力資産担保証券)方式を用いた発電所建設費用の回収方法が検討されている。リスクが消費者や納税者に転嫁される可能性がある。
・汚染処理水の問題: 汚染処理水の排出が今後30年以上続く見込み。
・汚染土壌の処理: 東京ドーム10個分の汚染土壌が中間処理施設に搬入されており、2045年までに搬出予定だが、その搬出先はめどが立っていない。
・石破首相の原発に関する考え方:「3.11の教訓は決して忘れてはいけない。あの時に原子力災害というのがいかに恐ろしいかということを思い知ったはずだ」
「私は22年前に防衛庁長官をやっていた時、原発はどれくらいの攻撃に耐えられるのか子細に検討した。原発の安全性は最大限に高めていかなければならない」、その他水力発電の拡大や省エネ推進をなどの発言が2024年8月の総裁選候補時にはあった。しかしその後は、原発を推進する方向にシフトしつつある。
合宿の感想
 写真2 福島合宿 福島原発をのぞむ
写真2 福島合宿 福島原発をのぞむ
・中間処理施設での作業の説明を受け、事故処理に膨大な労力がかかっていることを実感した。
・長い間立入禁止区域だった場所は、今も時間が止まったようだった。
・原発事故による立入禁止区域では、津波被害後の救助活動が制限され、多くの命が救えなかったことを知り驚いた。救助隊員たちが今もトラウマに苦しんでいるという話が印象的だった。
・廃炉以外の方法を検討してもいいのではないかと思った。
・今回の福島合宿と今回の学びを通じて、原発事故の影響が今後30年以上にわたり私たちの暮らしに及ぶことを改めて認識した。エネルギー政策に関心を持っていないと、知らないうちに自分たちの将来にわたる大事な出来事が決まってしまうことに気づいた。
2. 杉並区の公営住宅(2年生)
本展示では、気候変動や環境対策について「どのようにすれば当事者意識を持つことができるか」をテーマに学んだことを発表しました。
特別授業の実施
この展示に向けた学びの一環として、2024年7月18日に特別授業を実施しました。ゲストスピーカーとして、工藤泰子氏(元日本気象協会 環境・エネルギー事業部 環境解析課 主任技師)をお迎えし、「気候市民会議をやってみる」というテーマで講義をしていただきました(https://meiji-commerce.jp/lesson/post-334.html)。
授業後に実施したアンケートでは、授業を聞いて今どのような気持ちか、2030年に自分や世界がどうなっていると思うか、の2点について、無記名で回答を収集しました。その結果、気候変動に対する無力感や、気候変動の影響を「自分ごと」として認識していない傾向が見られました。
エコ住宅のデザイン提案
この課題を受け、温暖化の進行や熱中症リスクの高まりを考慮しながら、「環境に配慮し、かつ人にとって理想的な公営住宅とは何か」を検討しました。具体的には、杉並区を例に、以下のようなエコ住宅のデザインを提案し、図示して展示しました。
・子育て支援施設の併設:安心して子育てができる環境の提供
・コミュニティスペースや子ども食堂の設置:地域住民との交流促進
・バリアフリー設計:高齢者や障がい者に優しい住環境
・農園の併設:自然とのふれあい、自助の場としての活用
・再生可能エネルギーの活用:省エネルギー住宅による快適な室温管理と熱中症防止
など
杉並区長の講演の聴講
また、2024年10月24日には、大学院教養デザイン研究科の特別講義に杉並区長・岸本聡子氏が登壇され、その講演を聴講しました。講演では、社会問題に対して無力感や閉塞感を抱きがちな私たちに対し、ヨーロッパの「ミュニシパリズム(地域主権主義)」の事例を紹介いただきました。アムステルダムやベルギーでの活動や暮らしの実体験をもとに、地域が主体となる社会のあり方について学ぶ機会となりました。
さらに、岸本区長の「さとこビジョン」の紹介を受け、選挙への関心を持つことの重要性について考える機会となりました。この流れを受け、学園祭の展示では選挙に関する情報も取り入れました。
3. 体験型コーナー(4年生)
4年生は、環境問題を楽しく学べる体験型コーナーを企画しました。

写真3 つかめる水の体験コーナー
(1)つかめる水
「つかめる水」は、アルギン酸ナトリウムと乳酸カルシウムを用いて、水を球状に固める実験です。この体験を通じて、ペットボトル削減の可能性について考えてもらうことを目的としました。参加者には実際に「つかめる水」を作る体験をしてもらいました。(衛生上の問題から、飲むことはできませんでした。)
また、ポスター展示では、マイクロプラスチックに関する研究成果などを紹介し、環境問題への理解を深めてもらう機会を提供しました。多くの来場者、特に子供たちが興味を持ち、積極的に参加してくれました。
(2)環境カルタ
環境問題に関するキーワードや豆知識が書かれた「環境カルタ」を用いたゲーム形式の学習コーナーを設置しました。幼児から大人まで幅広い年齢層の参加者が楽しみながら環境について学ぶことができました。