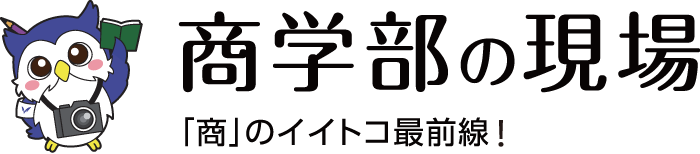2025.01.11
商学部生のボランティア活動
商学部3年 近藤 源斗〔商学部の現場〕編集記者
こんにちは。商学部3年学生記者の近藤源斗です。
みなさんは、「商学部」と聞くと、簿記や経営・マーケティング科目のみ勉強しているイメージはありませんか? 僕も高校生の時にはそのように感じていました。実際に1、2年次では必修科目である経済学や選択科目の簿記と経営学総論などを履修していました。それだけでなく、選択科目では日本文化史や社会学、哲学、地理など、ビジネスに関係がなさそうな授業も多く受けていました。その後3年次で専攻を決め、交通論やマーケティングを勉強しています。このように商学部は、1、2年次で幅広く学問を学んでから自分の専攻を決めるカリキュラムで、入学後に授業や課外活動などで自分の興味や知識を広げられます。色々な学問を学びたい、課外活動で多くの経験をしたい人にはとてもおすすめです。この記事では、課外活動に取り組む商学部3年生の高橋千穂さんにインタビューしました。高橋さんは、体育会の中で積極的にボランティア活動を行うローバースカウト部に所属しています。ボランティア活動に興味はあるけど、実感がわかないなと感じる方は是非この記事を読んで、少しでも興味を持ってもらえれば取材した記者として嬉しい限りです。
ローバースカウト部について
ローバースカウト部は、創立100年あまりを迎える体育会の部活動で現在は約70名在籍して活動しています。商学部の学生も17人所属しています。主な活動内容は、①野営(部内では野営と呼んでいる移動キャンプ)と②奉仕(ボランティア)の2つです。①の野営は、夏休みに実施していて今年は9泊10日で北海道の釧路から網走までの150kmを徒歩のみで踏破する移動キャンプを行いました。②の奉仕活動は、1923年の関東大震災を受けて始まり、阪神・淡路大震災・中越地震・東日本大震災でも奉仕活動を行いました。2014年から始まった東日本大震災の被災地での奉仕活動は現在も継続しています。福島県新地町と宮城県気仙沼市で子どもを集めて、デイキャンプを開催しており、この企画は自分たちで企画から運営まで行います。またデイキャンプのほかに、新地町の活動では地元のお祭りの手伝いとして魚を焼くことやゴミの分別を行っています。高橋さんも2年生の時には気仙沼市の活動に、1年生と3年生の時には新地町の活動に参加されたそうです。
能登半島地震後の奉仕活動について
ローバースカウト部は、2024年の1月1日に発生した能登半島地震を受けて、石川県七尾市が呼びかけたボランティア活動に参加しました。震災直後には新宿や下北沢など若者が集まる都内で募金活動を実施し、その後に現地での活動を行いました。活動を行うため、ローバースカウト部監督のOBが勤務する会社が、現地での部員の宿泊先の手配をしてくれました。ボランティアの参加にあたっては一緒にがんばろう、復興を目指そう、という思いのもと部内で「ともに」というテーマを立てて活動したそうです。またオリジナルのジャンパーを作成し現地で着用しています。
ここからは、その活動に参加した高橋さんの話を紹介します。
――高橋さんが七尾市でのボランティア活動に参加した理由を聞いてもいいですか。
七尾市での活動は、部としては任意参加でした。しかし震災当日この出来事をニュースで知ってから、ただ家にいる自分が何もできないことにもどかしさを感じ、少しでも被災した方の力になればと思い参加しました。私自身、ローバースカウト部に所属し東北地方のボランティア活動に参加する中で、ニュースで報道される災害に関して当事者意識を持つようになり、ボランティアに参加して周りの人を助けたいという気持ちが強くなりました。だから、もしローバースカウト部に入部していなかったとしたら、今回の震災も他人事のように捉えていたかもしれません。
――活動の中で感じたことや印象に残っていることは何かありますか。
部全体では1か月間交代制で実施していましたが、私は2泊3日で参加しました。現地では、七尾市のボランティアセンターの指示のもと、私のチームはトイレ清掃などの避難所の片付けや被災された個人宅を訪れ、家財の運び出しを行いました。私が参加したのは3月だったため現地では崩壊している建物がそのままだったり、道のマンホールが浮いているところもありました。そんな状況を見て、復興が追いついていない、報道よりもリアルな能登の現状を感じました。中でも印象に残っていることは、個人宅で家財を運び出したときことで、その様子を眺める住人の方のただ呆然とした表情です。その表情を見たときに被災された方のやるせなさや言葉にできない何かを感じました。
ボランティアについて
――高橋さんが考えるボランティアのやりがいや意義は何ですか?
大した自分じゃないけれど、少しでも誰かの力になれること、ありがとうと言われた時にやりがいを感じます。ボランティアの意義は先ほどの話と被るところがありますが、実際に参加することで報道では分からない現地の空気感を肌で感じられること。そこから自分の価値観を見直すことや社会に対して当事者意識を向けられることだと私は思います。
――最後にボランティアに参加しようと考える学生に向けてメッセージをお願いします。
ボランティアは、自分の価値観や社会に対する意識を変えられるきっかけになります。もし参加することを迷っていたら、ぜひ第一歩を踏み出してみてください。
――今日はありがとうございました。高橋さんの話を聞いて僕もボランティアに参加してみたいと思いました。
こちらこそ、ありがとうございました。

- ジャンパーを着用した七尾市での写真(中央が高橋さん)
記者自身、ボランティアに最後に参加したのは、中学生の時のあしなが募金でした。大学に入ってから興味はあったものの、中々踏み出せずにいましたが、今日の話を聞いて誰かの力になれるなら参加したいと思いました。明治大学には4つのキャンパスにそれぞれボランティアセンターがあります。実際に、地域で行われる活動も紹介しており、学生が取り組みやすい環境も整っています。もしボランティアに参加してみたいと思った明大生は、所属するキャンパスのボランティアセンターを訪れてみてください。
・明治大学ボランティアセンター | 明治大学
・明治大学体育会ローバースカウト部 ホームページ
・ローバースカウト部の紹介記事