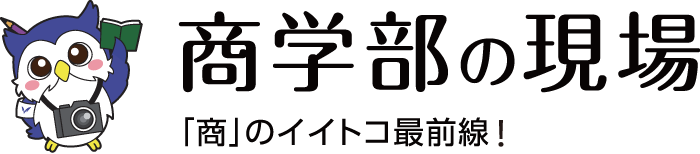2025.08.21
特別テーマ実践科目A「イスラーム世界実践探求Ⅰ」成果報告会
ハディ ハーニ(担当教員)
2025年度春学期の『特別テーマ実践科目A(イスラーム世界実践探求Ⅰ)』では、現代世界においてますます重要性を増すイスラームについて、多角的な視点から理解を深めることを目的として活動してきました。
本科目の目標は、イスラームに関する基礎知識を習得した上で、学生一人ひとりが主体的に課題を発見し、リサーチクエスチョンを設定し、実践的な調査・研究を行うことにあります。日本では、ムスリム(イスラーム教徒)の人口が増加傾向にあるにもかかわらず、イスラームに関する理解は未だ十分とは言えません。この「知識のギャップ」を埋めるべく、春学期は基本文献の精読に加え、東京ジャーミイへの訪問や、学内コンビニにおけるハラール食品の調査といったフィールドワークを重視し、実践的な学びに繋げてきました。
期末レポートは、春学期の集大成として、各自が設定したテーマに関する調査・考察をまとめたものです。受講生たちの関心は多岐にわたり、それぞれがユニークな視点からイスラーム世界を探求しようとする意欲的な内容となり、発表会では活発なディスカッションが行われました。以下にその成果の一部を概観します。
1. イスラームと現代社会・経済の接点を探る
多くの学生が、イスラームを古典的な宗教体系としてだけでなく、現代社会が直面する課題と密接に関わるアクチュアルなテーマとして捉えました。例えば、AI(人工知能)がイスラーム法においてどのように解釈されうるのか、特に「AIがファトワー(法的見解)を発行できるか」という最先端の問いを探求したレポートがありました。また、自身の専門分野と結びつけ、イスラーム法に準拠した相互扶助の仕組みである「タカーフル(イスラーム保険)」や、世界的に拡大するハラール市場、特にハラール日本食のビジネス的可能性について、具体的なデータや事例を基に考察したレポートも見られました。これらは、イスラームがテクノロジーやグローバル経済とダイナミックに関わる様相を的確に捉えています。
2. 思想・歴史・文化の深層に迫る
イスラームの思想的、文化的な深層に迫るレポートも複数提出されました。アブラハムの宗教(ユダヤ教、キリスト教、イスラーム)における「預言者」の概念を比較分析し、共通性と差異を浮き彫りにした研究は、イスラームをより広い文明史的文脈で理解しようとする試みです。また、西洋哲学とイスラーム哲学の関係性を探り、イスラーム哲学が西洋に与えた影響や、しばしば見過ごされがちな知的伝統の豊かさを論じたレポートは、ヨーロッパ中心主義的な歴史観を問い直す鋭い視点を含んでいました。さらに、ムスリム女性の「ヒジャーブ(ヴェール)」をテーマに、その歴史的変遷や、現代社会における「着る自由」と「着ない自由」をめぐる複雑な議論を丹念に追った研究もあり、一つのシンボルからイスラームの多面性を読み解こうとする姿勢がうかがえました。
3. 現代世界が直面する課題への視座
今日の国際社会が直面する困難な問題に、イスラームという視点からアプローチするレポートも目立ちました。特に、多くの学生がパレスチナ問題を取り上げました。その歴史的背景を、イギリスの「三枚舌外交」に代表される20世紀初頭の帝国主義の動向から説き起こし、紛争の根源を構造的に理解しようと努めました。また、ヨーロッパにおける政教分離の理念と、移民の増加によって存在感を増すイスラームの価値観との間で生じる摩擦や共生の可能性を、フランスのライシテやスカーフ論争を例に考察したレポートもありました。これらは、ニュースの向こう側にある複雑な歴史的・社会的文脈を読み解き、当事者の視点に立って問題を考えようとする真摯な態度を示しています。
4. 日本におけるイスラームの探求
イスラームを「遠い世界」の出来事とせず、日本社会との関わりにおいて捉えようとする視点も、本ゼミが重視する点です。カトリックの学校で育った経験から、なぜ日本人がイスラームに改宗するのか、その内面的な「魅力」とは何かを探求したレポートは、独自の切り口が光りました。そこでは、日本人ムスリムの多様な生き方や歴史が紹介され、ステレオタイプではないイスラームの姿が描き出されています。
総括と今後の展望
春学期の一連のレポートは、学生たちが文献調査とフィールドワークで得た学びを基に、各自の関心を発展させ、多様なリサーチクエスチョンを設定できたことを示す、大きな成果と言えます。どのレポートにも共通しているのは、イスラームを一枚岩として捉えるのではなく、その内にある多様性や歴史的・社会的文脈を理解しようとする姿勢です。
秋学期は、これらのレポートで提示された課題や問いをさらに深化させ、より学術的な方法論に基づいた本格的な研究へと発展させていく予定です。学生たちが自ら設定したテーマを粘り強く探求し、知見を深めていくプロセスに大いに期待しています。
(最終成果報告会の様子)