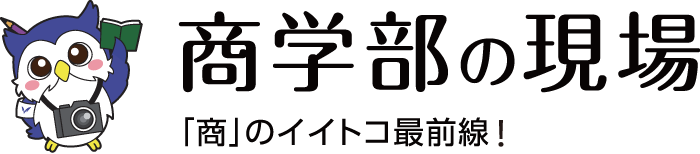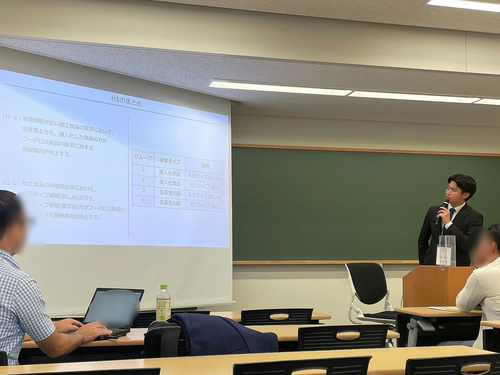2025.10.14
加藤拓巳ゼミの学生が日本マーケティング学会カンファレンス2025にて研究成果を発表
加藤拓己(担当教員)
2025年10月12日の日本マーケティング学会カンファレンス2025にて、加藤拓巳ゼミの学生が以下5件の研究成果をフルペーパーとして発表しました。
小澤裕太・加藤拓巳. (2025). 生産者の顔が見えない加工食品におけるフードロス削減に向けたコミュニケーション. 日本マーケティング学会カンファレンス・プロシーディングス. https://www.j-mac.or.jp/oral/dtl.php?os_id=581
概要:エシカル消費を推進するためには,社会や他者の利益である利他的動機ではなく,消費者の個人的利益である利己的動機を強調する必要性が認識されている。よって,利己的動機を強化するためのコンセプトやデザインが議論されてきた。しかし,小売でのフードロス削減では,その対応が難しい。なぜなら,商品の消費期限の違いだけであるため,商品の設計を変更することができない。その結果,これまで値引きが唯一の施策になってきた。値引きは短期的な販売促進にはなっても,長期的には利益率低下に加え,ブランドイメージやロイヤルティの低下というデメリットがある。生産者が見える農産物では,マーケティングコミュニケーションの観点から,農家の顔写真やメッセージを添える対策が取られているが,生産者の顔が見えにくい加工食品ではそれも困難である。そこで,即席めんを対象とし,主体(生産者の顔,擬人化商品)と感情(悲しみ,喜び)に着眼して,値引きと同等の効果を発揮する訴求方法をランダム化比較試験で検討した。商品を擬人化し,喜びの感情を用いることで,20%引きと同等の魅力を引き出す効果を示した。
丸山実花・加藤拓巳. (2025). AIエージェントにおける効果的な情報提供方法の検討 ― アイコン・選択肢の数・負の側面の観点からの実証 ―. 日本マーケティング学会カンファレンス・プロシーディングス. https://www.j-mac.or.jp/oral/dtl.php?os_id=558
概要:現在,急速に市場が拡大している人工知能エージェント(AIエージェント)は,性能競争が加熱している。しかし一定レベルを超えた段階で,消費者視点では過剰なレベルに達する懸念がある。この時,次に必要になる視点の1つがユーザー経験(UX)であるが,現時点でこの知見は限定的である。そこで,「AIエージェントとの対話において,誰が,どれだけ,どのように情報を提供すべきか?」というリサーチクエスチョンを設定し,3つのランダム化比較実験により検証した。STUDY1では,AIエージェントにおいてアイコンのデザインがユーザーの印象形成に与える影響が限定的であることが分かった。STUDY2では,中程度の選択肢数の提示は,ユーザーに十分な比較検討の余地を与えつつ,過度な認知的負担を回避し最適であることを示した。STUDY3では,提案の質を高める要素として,推奨事項や肯定的側面に加えて,否定的側面を示すことが効果的であった。本研究結果は,将来的に競争力の源泉として不可欠になるAIエージェントのUX設計に有益な示唆を提供している。
田中美桜里・岩井隆宏・チョブギョン・武藤結衣・加藤 拓巳. (2025). エシカル消費における時間と季節による商品価値の変動 ― 食品業界を対象としたコンセプトとデザインの視点からの検証 ―. 日本マーケティング学会カンファレンス・プロシーディングス. https://www.j-mac.or.jp/oral/dtl.php?os_id=560
概要:エシカル消費の訴求は,環境配慮や人権保護という利他的要素が中心となってきた。しかし,消費者に直接的な価値となる利己的要素を提供しない限り,エシカル商品は社会に根付きにくい。利己的要素は,主に機能的価値と情緒的価値があり,近年は後者の重要性が認識されている。情緒的価値は消費者を取り巻く環境によって価値が変動する。そこで,本研究は,エシカル商品に時間軸という環境を導入した。「時間帯と季節により,エシカル商品の価値は変動するか?」というリサーチクエスチョンを設定し,2つのランダム化比較試験を実施した。エシカルコーヒーとエシカルカレーを対象としたSTUDY1では,「朝の道徳効果」によって,朝の利用を強調した商品コンセプトを採用することにより,商品の魅力を高めることを示した。カフェラテのボトルデザインを対象としたSTUDY2では,商品の擬人化により,「ラベル=服」と見立てると,涼しい印象を与えるラベルレスデザインは,夏におけるコールド飲料で魅力が高まることが示された。社会的に意義の大きなエシカル消費を促進するためには,時間軸による価値の強化という視点は有効である。
清水碧音・秋本光紀・河西淳志・林咲希・重野ゆら・加藤 拓巳. (2025). AIエージェントにおける専門家コンセプトがサービス魅力度に与える影響. 日本マーケティング学会カンファレンス・プロシーディングス. https://www.j-mac.or.jp/oral/dtl.php?os_id=567
概要:現代社会におけるフェイクニュースの拡散は,生成AIの登場により急速に深刻化しており,世界的に喫緊の社会問題として認識されている。AIエージェントは情報収集・真偽確認の手段として注目されるが,誤った情報や誤解を招く情報を含む回答を提供するハルシネーションの懸念から,利用者自身での参照元確認の必要がある。つまり,現状ではフェイクニュース問題の解決には至っていない。そこで本研究は,AIエージェントの学習範囲と利用用途を限定することで,この問題解決の一助となるサービスコンセプトとして,「情報源と用途を専門家の知見に限定するコンセプトはAIエージェントの魅力を高めるか?」をリサーチクエスチョンとし,2つのランダム化比較試験を実施した。STUDY1では,AIエージェントのコンセプトにおいて,専門家による確かな情報がキュレーションや共感よりも魅力を高めることを示した。STUDY2では,診療場面におけるAIエージェントにて,専門知識に基づく話し方の体験(UX)の魅力を検討した。本研究の結果は,世界的に性能競争が激化しているAIエージェント市場に対して,コンセプトという新たな視点の価値を示した。
高橋耀生・奥澤知世・中村梨琴・石尾美里・大坪稜・加藤 拓巳. (2025). 消費者の心理的問題を解決するVRのサービスコンセプトの開発 ― 中間管理職の心理的負担の解消を題材とした検証 ―. 日本マーケティング学会カンファレンス・プロシーディングス. https://www.j-mac.or.jp/oral/dtl.php?os_id=555
概要:近年,中間管理職は過重な業務や責任を負いながら,キャリア不安を伴うミッドライフクライシスが重なり,深刻な心理的負担を抱えている。この状況は昇進意欲の低下や管理職不足につながる組織課題となっている。その解決策として,現実逃避によるストレス軽減と,転職に向けた他の仕事の適性確認の2点が考えられる。本研究では,これらを同時に支援する手段としてVR(仮想現実)サービスに着目し,「中間管理職はVRゴーグルにおける違う人生の経験というコンセプトに魅力を感じるか?」というリサーチクエスチョンを設定した。オンライン調査環境でのランダム化比較試験にて,3つのコンセプト(最新技術,没入感,違う人生の経験)の魅力への効果を比較した。全体としては「没入感」が最も高く評価されたが,当該コンセプトと管理職の交互作用を含めた重回帰分析の結果,「違う人生の経験」は中間管理職においては上昇傾向が見られた。以上より,VRは中間管理職問題に対応し得る手段の1つと考えられる。この結果は,VRという新しい技術を普及させるには,技術的優位性だけでなく,消費者の問題を解決するコンセプトの検討も重要であることを示唆している。