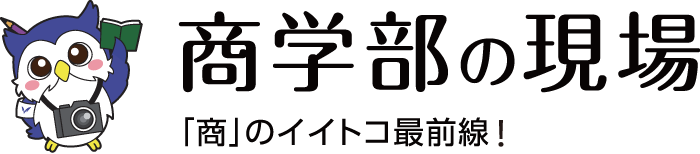2025.11.20
ゲストスピーカーによる特別授業実施報告:立川がじら氏【テーマ:話芸の日本語表現】
石出靖雄(担当教員)
1.実施日
2025年11月17日(月)10:50 ~ 12:30
2.実施場所
和泉ラーニングスクエア501
3.科目名
日本語表現論B
4.ゲストスピーカー
立川がじら氏(肩書:落語立川流二つ目)
5.実施内容
落語立川流の立川がじら氏より、落語の実演をしていただきました。そのほか、落語立川流の立川笑王丸氏にもご参加いただきました。お二人とも明治大学落語研究会のご出身で、現在プロの落語家として活躍されています。
はじめに、立川がじら氏が高座に上がり、落語入門とでもいうべき基本的な落語知識をレクチャーされました。落語では上半身だけで演技するということや、演じるときに扇子や手ぬぐいを使うことなど、実演を交えて紹介なさいました。その後、古典から現代風までの小噺の面白さを紹介されました。落語がヨーロッパの笑いまでも取り入れていることを教示されました。
つづいて、立川笑王丸氏が前座として高座に上がりました。拍手のタイミング、落語がスピークではなくトークであること、落語家と聴衆が協力して落語を作り上げていくことなどを語られ、会場の雰囲気を和ませていました。演じられたのは古典落語の「牛ほめ」でした。
「牛ほめ」は、ぼんやり者の与太郎が、おじさんの新築した家をほめに行く話です。難解な挨拶の文句を覚えるシーンや、ほめに行ったものの間違えてしまう場面など、山場の多い話でした。現代の学生にもわかりやすいように何気なく解説を混ぜたり、理解の難しい言葉は省略したりするなどの配慮がなされていました。
最後に、立川がじら氏が高座に上がり、古典落語の「死神」を熱演されました。マクラでは、高座名の由来(師匠の「志らく」の2文字を入れて「がじら」であること、「談笑」の弟子なので「笑王丸」であること)や、落語は音楽に近いため同じ話を何度聞いて飽きないことなどを話され、さらに古今東西の小噺を話されました。
「死神」は初代三遊亭圓朝がヨーロッパの話を翻案したものと言われたもので、いわゆるオオネタと言われる本格的な噺です。昭和では圓生などが得意としていました。がじら氏の師匠である立川志らく氏も高座にかけています。最後の落ちの部分は圓朝のものを使わずに独自の工夫がなされていました。また、作中の呪文は「あじゃからかもくれん」から始まる有名なものですが、がじら氏は「あじゃらかもくれんラーニングスクエア...」と学生のために変更していました。
これらの落語の舞台は、現代と生活様式の異なる江戸から明治時代ですが、がじら氏は言葉を選び、また現代の用語に置き換えるなどの工夫を行い、非常に分かりやすい落語に仕上げていました。
演じられた噺は古典落語ではありますが、その中に現代風なアレンジがほどこされており、落語が現代にも根付いている話芸であることが実感できるものでした。